中1の2学期、不登校開始。
中学受験を終えて何もかもが新しい中学校生活がはじまり、学校生活に馴染んでるとは思えない息子の様子を心配してはいたものの、静かにその時は訪れた。二学期の始業式の日。
「俺、学校行きたくないんだけど。」
そう来ることを心の何処かで予想はしていたので、受け入れるのに迷いはなかった。
「そうか、わかったよ。行かなくていいよ。」
そうして息子のスローライフが始まった。
特にこれまで発達の問題を言われたことはない。おいおい語っていきたいが、色々な要因が重なってこの日を迎えた。性格が真面目なだけに、一度止めてしまった通学という習慣、始めてしまった不登校は、ある日気分でコロッと通学を再開することはないだろう。そもそも、自分と真剣に向き合ったからこそ自分の気持ちが見えたのだと思う。
気の合う友達がいなかったことと、授業の雰囲気が悪かったりつまらなかったりして辛いみたいだ。
小学校の高学年はほとんど遊びにも行かずに中学受験に向き合ったことが間違っていたのだろうか…と何度も思った。
しかし、1ヶ月経って、色々な原因が少しずつ見えてきた。
中学受験をするイコール間違いか、間違っていないか、という単純な因果関係で片付けることに意味はなく、我が子が何に躓いたのか、何を感じたのか、1つ1つわかろうとすれば、1つ1つ我が子のことがわかっていくのだと思う。
息子にとっては第1志望ではなかったものの、結果的にとてもいい学校にご縁を頂いたと私は思っている。とても不登校に理解があり、学校に無理やり来させられるようなことはない。なんと勉強もしなくて良い。私立でよかった。公立だとなかなかこうはいかないはずだ。ただ、公立だとしても最近はドワンゴのN中のようなオンラインスクールやフリースクールがあるので、なんとかなるものだなと思った。
結局我が子は、そのようなフリースクールは現在のところ選択せずに、自宅学習+塾を探すことと、時々先生と面談というか交流する機会を設けてもらって学校と繋がることになった。
学校へ行かないということを選択して以降、たった1ヶ月ではあるものの、息子は色々と人生において重要な判断をした。例えば、嫌なものを嫌ということだ。苦手な仲間とは距離を置いていいということや、集団で授業を受けたくないと発言すること、N中は今は受けないという選択も息子が自分で判断した。それから、不登校初期はYou Tubeをとにかく辞めさせようと私達親は躍起になったのだが、2日ほど我慢したあと、「俺はYou Tubeを見るかどうかを人に決められたくない。自分で決めたい」という結論を伝えてきた。これも息子の選択だ。これについては、早寝早起きを守って食事も時間通りに家族と摂っており問題ないので、受け入れることにした。
それから、不登校になってすぐにスクールカウンセラーを予約したが、ついてきてくれたこと。少し迷ってはいたものの、私の提案を受け入れてくれたのだった。スクールカウンセラーでは、口数は多くないものの、素直に話していた。
ただ、2回ほど行ったところで、もう自分にはカウンセラーは必要ないということになり、行かないことになった。今度は一緒に担任の先生と面談に行こうと誘ってみた。これも前日まで渋ったが、受け入れてくれ、先生と面談してみたところ案外楽しそうに過ごしてくれた。そして今度は先生の提案を受け入れて、月に1回程度先生と二人の時間を作ってもらって過ごすことになったのだ。これは母親の私から見てかなり画期的な出来事だった。集団での授業を拒否した息子が自ら選択した道がこのように拓かれてきているのが嬉しかった。
受験期間中、そして入学後の1学期は、家族と出かけることもことごとく断って自分の世界に籠もり続けていた。それも息子の選択だったから、間違ったことはないと思う。
これから、息子が学校という場を少し減らした生活においてどう興味を拡げ成長していくか、母として見守りながら奮闘していきたい。
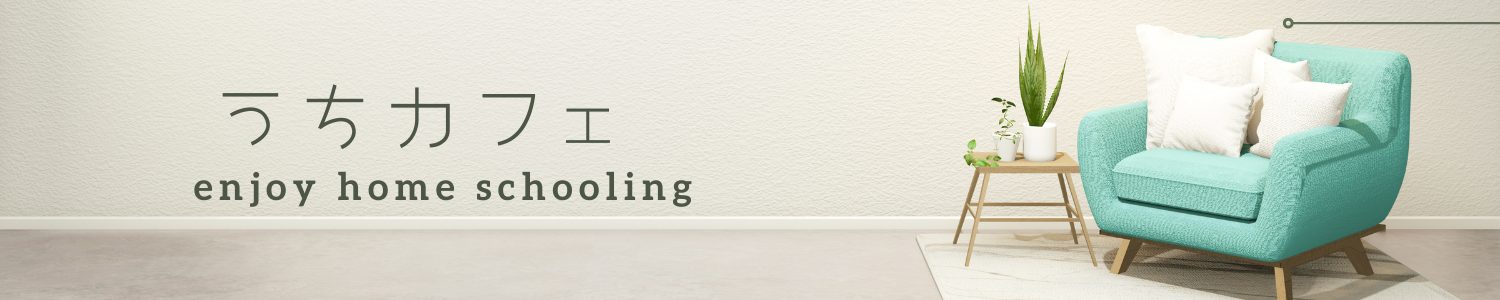



コメント