僕たちはどう生きるか 言葉と思考のエコロジカルな転回
森田真生
コロナ禍で我が子と自然とともに暮らした1年のエッセイである。著者は独立研究者の森田真生さん。
息子の入学式で先生より紹介された本で、すっかりはまってしまった。森田さんの知性と人格が生み出す、生命への愛で溢れた文章。我が子の言葉や行動の1つ1つを見逃さず、それらに映し出された暮らしの変化、自然の姿、子どもの感性が丁寧に描かれていく。
こんな風に子育てできたら良かった…という憧れをつい感じてしまう。
しかしね。五感から入ってくる情報からこんなにも深い言葉と思考が紡ぎ出されるのは、誰にでもできることではない。森田さんは数学の研究者で、そして何でもできる人(私の表現力よ…)。
コロナウイルス感染拡大という状況にミクロの異変、気候変動、そして経済活動停滞による環境の浄化など様々な自然現象に対する考察が述べられていくが、人と自分の関係、環境と自分の関係について森田さんの中にある深い思考がそこかしこに挟み込まれており、私の未熟な思考に刺激をもたらしていく。それが、息子が今通学を中止して過ごしている時間のことを記述しているような気がして涙が出そうになる。
異質な他者の存在をゆるし、それと付き合いながら少しずつ調子を合わせていくこと。これをモートンはattunementとよぶ。(中略)波長を合わせていくこと、適応していくこと、自分でないものに少しずつ慣れていくことなどを含意する豊かな意味の広がりを持つ言葉である。他者を排除するのでもなく、他者に耳を傾け、付き合っていくこと。自分でないものと共存しながら、それでいて容易に一体化してしまわないこと。
すべてのものは、自力でないものに支えられている。だから、自力で立てるものなどない。この意味で、人に限らず、ものはみな弱い。弱さは、存在の欠陥だけでなく、存在とはそもそも弱いものなのだ。
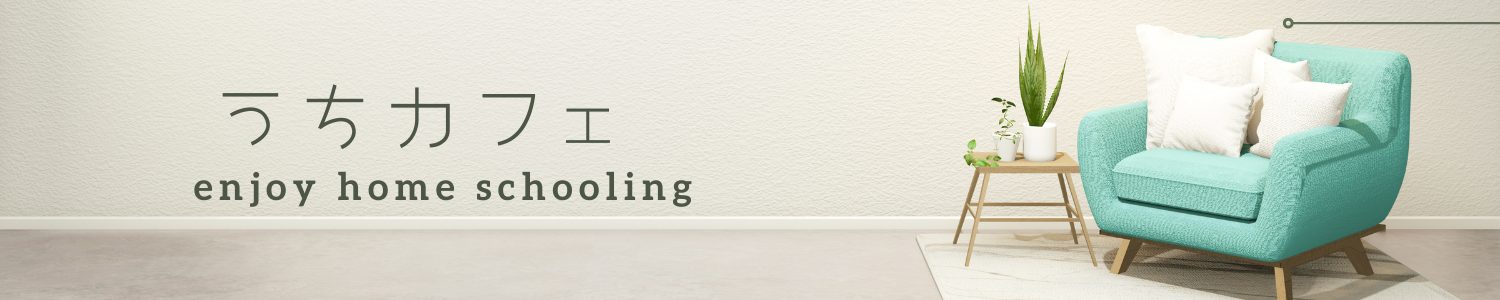



コメント