声かけで伸ばす 内向的な子のすごい力
-臨床心理士・公認心理師 吉田美智子 著- ディスカヴァー
グレーゾーンでも発達障害でもなく、人間の心が内向きか外向きかあるいはその中間にあることに着目し、内向きの中でも3つのパターンがあるという定義についてわかりやすく解説してくれている本。
自分の子どもが学校生活に向いていないことが明らかになって、どこに問題があるのか、
どんな目標や将来像を描かせてあげられるのか、簡単には答えが出ない。学校に行かないから障害がある、情緒や問題がある、といった可能性に向かっていく前に、内向き型だという事実を受け止めておくべきだったんだ…ということに気付かされた。
何人かの精神学者の理論が紹介されているが、内向型・外向型の研究知られているのがユングなのだそう。ユングという人の名前は何度も聞いたことあるのに全くの不勉強だった。
この本では内向的な子のタイプを「内向型」「HSC型」「トラウマ型」と3つに分類している。
我が子は内向型に当てはまりそうなので、内向型の特徴を以下に引用。
【内向型の子どもの傾向】
ひとりを好む、自分の世界がある、マイペースな子ども。
【内向型の子どもの悩み】
「みんなと一緒」がストレスになる。
【対応方法】
本人のペースとスペースを尊重する。
本当に、うちの息子もこれなのである。一方HSC型とはHighly Sensitive Child の頭文字を取った用語であり、「感じやすく影響を受けやすい、環境感受性の高い子ども」とのこと。内向型と見分けづらいけれど、自分尊重タイプなのが内向型で、感じやすいのがHSC型なのだ。
そしてこれら内向的なタイプと逆の外交的なタイプとは、ユングの定義によると「日常的に自分の外界に対して興味関心を抱ける。好奇心が強く新しいことにチャレンジするのが好き」とされている。
母親である私が外交的なタイプであることもあり、内向的な息子に対し「好奇心がなくてチャレンジしない。心配な子」と定義してしまっていたということに気づいた。母親の特性と息子の特性が違うというだけで、息子を劣っているのではないか、不安要素があるのではないか、とマイナスに捉えてしまっていたのだった。
更に興味深いのは、米国のスーザン・ケインという人が2012年に出版した本によれば、アメリカにおいて工業化や都市化という社会の変化の過程で外向型がリーダーシップを取ってきたことにより、外向型が評価されるようになり、逆に内向型は克服すべき課題とみなされるようになったという背景があるとのこと。日本でも、日本の国民性がどちらかというと内向型であるにもかかわらず、やはり欧米のリーダーシップを学んでそのように評価される傾向がある。
何なら、学校そのものが、外向型の人間を育てることを目標とし評価しているのではないかという気もする。
そうだとすれば我が子は学校に行く必要はないのかもしれない。
この本では内向型やHSC型のいいところも定義してくれている。
【内向型のいいところ】
自分なりの考えがある
独自の世界観がある
責任感がある
葛藤する力がある
どうだろう?なんとも嬉しくなってきてしまう。
内向的な我が子に対して不安を抱えている、我が子を変えようとしてしまっている、そんな親御さんにはぜひこの本をお勧めしたい。
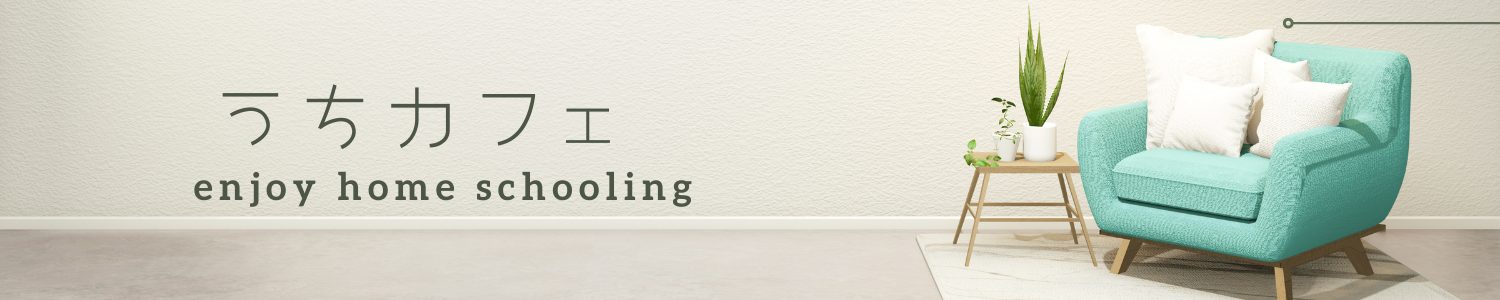


コメント